久々のどうする家康関連記事です。
物語が進むにつれて新しい登場人物のキャストが発表されています。
ネットではまだ発表されていないキャストの予想が盛り上がっていますね。
私が一番気になるのは、最後まで徳川家を苦しめ続けた真田昌幸・信繁親子です。
6/16に真田家3人のキャストが決まりました!
キャストの詳しい紹介は別記事で紹介します。
今回は今後『どうする家康』で起こりうる徳川家VS真田親子のエピソード3選をご紹介いたします。
常に少数で徳川の大軍勢に対抗した真田の戦い方は、とてもドラマティックです!
1.徳川家の宿敵?真田家とは
まずはじめに徳川相手に奮闘した小大名である真田家についてご紹介します。
真田家はもともと信濃の国(長野県周辺)の豪族でした。
戦国時代、武田家につかえる武将として名をあげてきましたが、武田家の滅亡に伴い戦国大名として自立しました。
独立した時の当主が真田昌幸、ゲームやアニメ、大河ドラマ真田丸で有名な真田信繫(幸村)のお父さんです。
家康が活躍する時代の真田家は当主の真田昌幸、長男真田信之、次男真田信繫(幸村)が活躍します。
徳川の敵として最後まで家康を苦しめた真田昌幸と真田信繁。
本多忠勝の娘と結婚し、徳川配下となった真田信之。
徳川家康と関係性の深い3人が『どうする家康』でどのように描かれるのかがとても楽しみです。
2.真田信繫(幸村)等のキャストは?
気になるのは真田信繫(幸村)ら真田家の面々のキャストです。
3月の時点ではまだ公式に発表されていません。
直近の大河ドラマ『真田丸』では主人公真田信繁を堺雅人さんが演じていました。
普段は頭がキレる温厚な青年ですが、勇猛果敢な一面もある難しい役どころです。
松本潤さんより一回りくらい若い実力派俳優を期待します!
個人的に見た目は向井理さん、星野源さんが選ばれてくれると面白いなと思います。
しかし人気俳優が演じてしまうと、ただでさえ人気武将なので主人公の家康を喰ってしまう可能性があります。
人選がとても難しいですね…。
次に『真田丸』では草刈正雄さんが演じていた真田昌幸。
狡猾な渋いおじさんというイメージです。
ネット上では真田丸つながりで堺雅人さんを推す声が多いようですが、少しクリーンな感じがします。
最後に『真田丸』では大泉洋さんが演じたため癖のあるキャラに仕上がっていた真田信之。
真面目で頼りになるお兄さんて感じのイメージなので、誰がキャストに選ばれても驚きはなさそうです。
→6/16 真田家のキャストが決まりました!
真田信繁役に日向亘さん、真田昌幸役に佐藤浩市さん、真田信之役に吉村界人さんです。
詳細は別の記事で紹介します。
3.徳川家と真田家のエピソード3選
『どうする家康』でも描かれるであろう徳川家康と真田家のエピソードを先取りして3つ紹介します。
少しネタバレ要素もあるので史実を知らないまま楽しみたい方は、戻るボタンを押してください。
①第一次上田合戦
武田家が滅亡した後、真田昌幸はすぐに織田信長の配下に加わる決断をします。
しかし真田昌幸が信長配下になった3か月後、本能寺の変がおこり信長は討たれてしまいました。
信濃の地で上杉、徳川、北条の有力大名に囲まれてしまった真田昌幸は従属する大名を次々に変えてなんとか生き延びようとします。
徳川に従属していた時に、真田の地であった沼田領(現在の群馬県沼田市)を北条に引き渡すよう家康から迫られた真田昌幸。
当然受け入れられる要求ではなく、真田は徳川を離れ上杉家に従属する事を選びます。
これに怒った家康は真田攻めを決意、家臣の鳥居元忠、大久保忠世、平岩親吉を上田城へ送りました。
徳川軍の兵は約7000、一方上田城を守る真田の兵は1200。
圧倒的兵数の差で上田城二の丸まで攻め込む徳川軍でしたが、真田昌幸の策略で誘い込まれており真田軍の反撃にあいます。
城下に火を放った真田昌幸は混乱する徳川兵を鉄砲で狙い撃ち、徳川の兵は慌てて撤退を始めました。
すると近くの城に籠城していると思われた真田信之も加わり真田軍は追撃。
徳川軍は撤退しながらも徐々に兵数を減らしていく事になります。
最終的に真田軍の犠牲者40人に対し、1300人もの犠牲者を出した徳川軍は真田討伐をあきらめました。
この後真田家は豊臣家へ従属した事で秀吉の後ろ盾を得ることができ、徳川から攻められることはなくなります。
この戦で真田家は大名としての評価が高まり、本多忠勝の娘と長男信之の婚姻が決まったとも言われています。
『どうする家康』でお馴染みの家臣団である鳥居元忠、大久保忠世、平岩親吉が奮闘する戦なので、どのように描かれるかが楽しみです。
《追記》
最近記事にした6月に発売の【どうする家康 NHK大河ドラマガイド】をみると第一次上田合戦が描かれない可能性があります。
『どうする家康』では重要な家臣が討ち死にするような戦以外は端折られる傾向にあるので、真田親子の出番は少し先になるかもしれません。
②第二次上田合戦
第二次上田合戦が勃発したのは1600年、関ヶ原の戦いの時期です。
秀吉の死後、家康に従っていた真田昌幸は次男信繁と共に離反し西軍に味方します。
この時長男の信之は家康のもとに残り東軍として戦っています。
真田昌幸が西軍東軍どちらが勝っても真田家が滅ぶことがないように、真田家を二分したと言われています。
そして上田城に戻った真田昌幸は、関ヶ原へ向かう途中の徳川秀忠軍3万8000人と対峙。
3000人しか兵がおらず当初降伏する意思を見せていた昌幸だったが、降伏を先延ばしにしたうえ約束を反故にしました。
これは戦の準備をするための時間を稼ぐ昌幸の策略だったのです。
戦の準備ができた昌幸は秀忠に宣戦布告。
昌幸にだまされ激怒した秀忠は上田城を包囲しました。
すると昌幸は50の兵を連れて偵察がてら徳川軍を挑発。
急に総大将が現れるという挑発に乗ってしまった徳川軍は一斉に攻撃を開始します。
昌幸は自身を囮に徳川軍を引き付けて、鉄砲で一斉射撃という策に出ます。
一斉射撃を受けた徳川軍は押し寄せる自軍の兵士に阻まれ撤退ができませんでした。
さらに伏兵が襲い掛かり、徳川軍は大混乱。
その隙をついて信繁が200の兵を率いて、手薄になった秀忠本陣に突撃します。
予想外の反撃を受けた秀忠は撤退。
その後家康から関ヶ原へ急ぐよう命を受けた秀忠は、真田討伐をあきらめて関ヶ原に進軍します。
しかし上田城での苦戦、途中の悪天候もあり関ヶ原の合戦当日には間に合いませんでした。
真田昌幸の【秀忠本隊足止め】という任務は無事成功したのです。
徳川軍の主役は家康の跡継ぎ秀忠です。
家康が直接指揮していない戦なので『どうする家康』ではどのように描かれるのでしょうか?
③大阪の陣
【大坂の陣あらすじ】
徳川家康最後にして最大の危機が、豊臣を滅亡させるための戦い大坂の陣です。
関ヶ原の戦いで勝利し実質天下人になった家康でしたが、正式には関白である豊臣秀頼の方が上の立場でした。
秀頼の存在が邪魔な家康は、「秀頼が復興させた寺が徳川に対して無礼な事を鐘に書いている」といちゃもんをつけるのです。
このことを理由に家康は豊臣家に無理難題を突き付けると、徳川家と豊臣家の関係は一気に悪化。
家康が各地の大名に豊臣討伐のため出兵するよう命令、豊臣家は秀吉時代の莫大な財産を使い浪人を雇い入れ戦力を整えます。
この時家康に不吉な報が届きました。
「真田が大阪城に入城」
真田昌幸は大坂の陣の数年前にこの世を去っているので、大阪城に入城したのは真田信繫(幸村)です。
しかし真田にトラウマを持つ家康は、「昌幸は油断させるために死んだふりをして豊臣方につき、自分の首を狙っているのでは?」と疑ったそうです。
【大坂冬の陣】
1614年、大阪冬の陣が開戦。
豊臣方は浪人を中心に10万人の戦力、徳川方は各地の大名から徴兵し20万人の戦力。
数で劣る豊臣方が大阪城に籠城し、それを徳川方の大名が包囲する形で戦は進みます。
この時徳川軍は大阪城の弱点である南側を攻めます。
しかし信繁はここに真田丸という出城を建設、徳川軍を迎え撃つ準備をしていました。
待ち構えられていた徳川の兵はここで大損害を出し、後退せざるをえなくなります。
その後徳川は無理に攻めようとせず大阪城を包囲しつつ、遠くから大砲で攻撃。
無理に攻めることができない徳川、包囲・砲撃に耐え忍ぶ豊臣という膠着した状況で双方の同意のもと和睦がなされます。
【大坂夏の陣】
堅牢な大阪城に籠城し善戦した豊臣勢ですが、大坂冬の陣の戦後処理で大阪城の掘りは埋められてしまいました。
さらに家康は冬の陣の時に雇い入れた浪人を雇い続けていることに対して秀頼に文句を言ってきます。
浪人を全員解雇するか、伊勢か大和へと転封するかという2択を迫られた秀頼はこの要求を拒否。
徳川家と豊臣家は再び対立する事になります。
徳川方15万人に対し、豊臣方は5万。
再び豊臣方の圧倒的不利で開戦します。
大阪城の掘りを埋められたせいで豊臣方の武将は不利な状況で野戦をするしかなくなります。
そして豊臣方の武将は徐々に撃破されていきます。
そんななか真田信繁は徳川家康の陣に向かって決死の突撃を敢行します。
1万5千もの大軍を突破し、徳川の親衛隊をも蹂躙したのち徳川本陣への突入に成功しました。
家康は本陣を捨て撤退、信繁の攻撃の勢いに2度も自害をしようとしたそうです。
しかしギリギリのところで信繁の猛攻から逃れた家康は、体勢を立て直し数で押し切ります。
決死の突入をした信繁も善戦むなしく、四天王寺近くの安居神社で討ち取られてしまいました。
最終的に大阪城は陥落、秀頼と淀殿は自害し大坂の陣は幕を閉じます。
徳川家康最後にして最大の危機となったので、『どうする家康』では真田信繫がラスボス的な描かれ方をするのではないでしょうか?
まとめ
今回は『どうする家康』で注目の真田家についてご紹介いたしました。
何回も言いますが、キャストがかなり楽しみです。
しかし最近『どうする家康』のペース配分について記事が出ていました。
内容はこのままのペースで大坂の陣まで描かれないのでは?というものです。
関ヶ原まででドラマ自体が終わってしまうと真田親子の出番はないかもしれません。
なんとか大坂の陣までやり切ってから終わって欲しいものです・・・。
|
|
その他『どうする家康』関連記事はコチラ
他の人気武将の記事はコチラ→【真田幸村】どうする家康であの人気武将の登場はいつ?【伊達政宗】
最後まで読んでいただきありがとうございます!
「今回の記事が役に立ったよ!」という方はブックマーク、Twitterフォローをお願い致します。

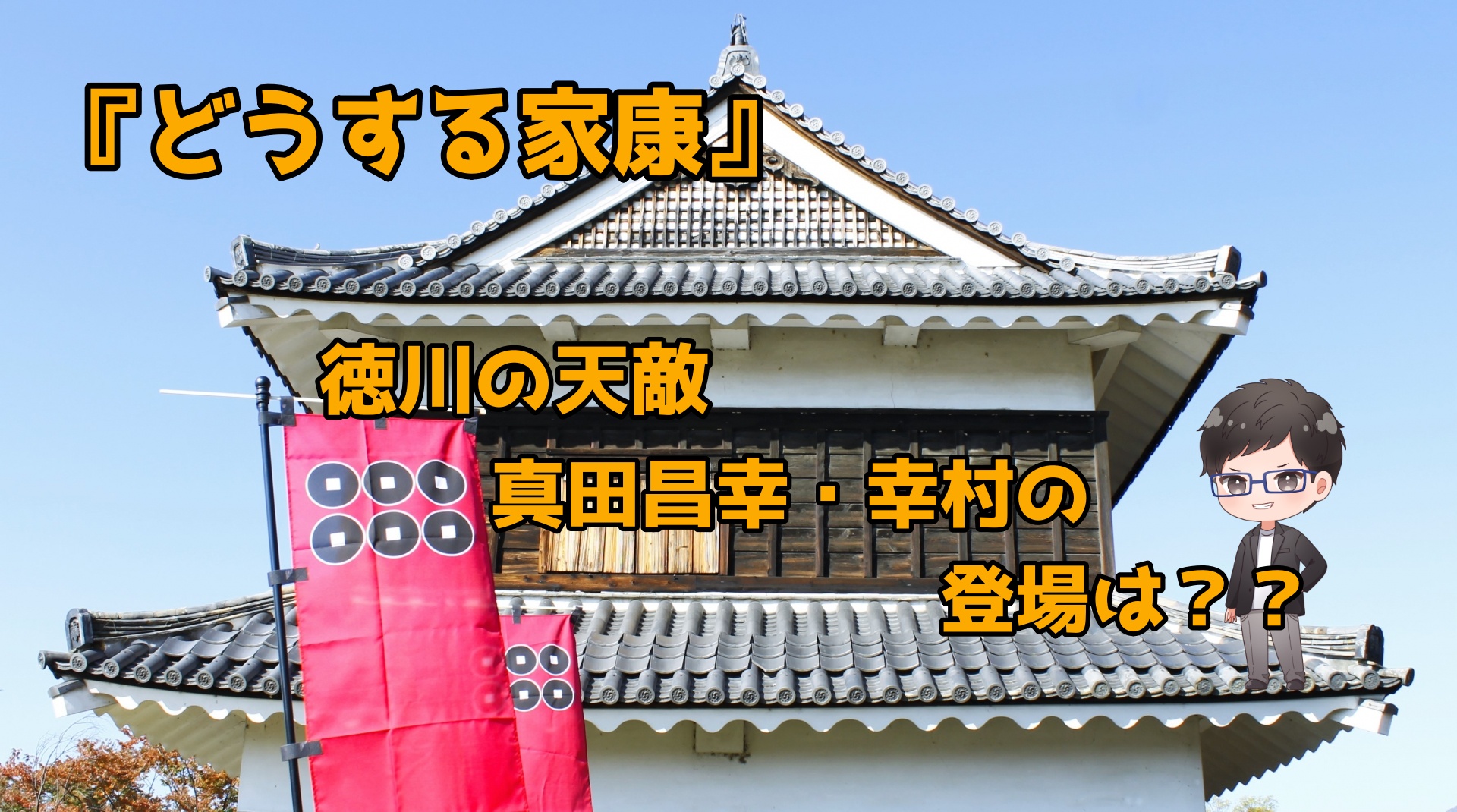






コメント
[…] というのも、この前書いた真田昌幸・幸村についての記事が結構読んでいただけています。 […]